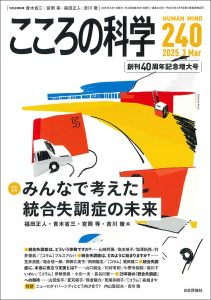【活動報告】2024年度東京都提言要望事項
精神障害当事者会ポルケは、ソーシャルアクションの一環として活動を通じた社会課題について、提言要望事項について行政や議会に届ける取り組みをしています。2024年の9月に東京都や都議会各派に提出した要望事項をご報告します。行政の職員や議員のみなさんと懇談を通じて、建設的な提案を今後も行っていきたいと思います。
■第8次保健医療計画の推進に係る提言事項
- 地域で安心して暮らせる体制づくり
東京都内における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムについては、国が行う構築事業および推進事業により促進がはかられていますが、具体的な取り組みについては自治体ごとのばらつきが出始めています。東京都内における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの底上げのために、各自治体での実施状況について各事業の好事例の集約を進めるなどした報告書を制作するなどして、東京都内の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの促進に向けた取り組みを加速していただきますよう提案いたします。東京都が既に実施をしている「東京都内の自立支援協議会の動向」のような形式で作成されると望ましいと考えます。
- 都民への普及啓発・相談対応の充実
メンタルヘルスの促進と精神障害への根深い偏見や差別の問題について、並行した普及啓発活動が必要と考えます。これまでの疾患予防の啓発はややもすると、現に精神障害のある人についてのネガティブなイメージを助長するばかりではなく、深刻な分断を招くことを憂慮いたします。障害者権利条約に即して、普及啓発活動については、当事者団体の参画を通じた内容の充実を促進してください。特に、優生思想の問題や若者へのメンタルヘルス教育、障害の合理的配慮についての項目は、当事者の意見を反映させてください。
また、高校の保健体育の授業でメンタルヘルスの内容が近年加わったことを受けて、学校教育への当事者会や家族会の出前講座の関わりが、にわかに広がりを見せています。都立高校での促進に向けた検討を進めてください。
- 精神科病院から地域生活への移行及び地域定着に向けた取り組みの推進
地域移行の促進の観点から、特に地域生活を送る退院後間もない精神障害のある人に対しては福祉支援の安定した提供が必要です。とりわけ、移動支援事業(地域生活支援事業)について、精神障害のある人への支援提供体制と質の向上が必要と考えます。「東京都精神障害者移動支援従業者養成研修課程」を新設し、精神障害のある人への移動支援の提供体制の促進に取り組んでください。
- 災害時における精神科医療体制の整備の推進
精神障害当事者会ポルケは、国立精神・神経医療研究センターらと協働し、精神障害のある人の災害時の困難についての質的研究調査に取り組んできました。この取り組みから、平時からの備えとして、精神障害の特性や被災時を想定した精神障害の医療福祉支援の確保等にかかる課題が明らかになってきました。個別避難計画等の作成の段階における的確な情報把握と避難生活後の暮らしを想定した備えが必要です。つきましては、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの項目に災害が新たに加わったことに鑑みて、精神障害のある人の実情にあわせた個別避難計画のフォーマットの改定や必要な支援の普及啓発について、東京都としての実施を今後新たに行ってください。そのためのヒアリングなどを当事者団体に行ってください。
- 精神科病院における虐待防止・人権擁護に向けた取り組みの推進
令和6年精神保健福祉法改正を受けて早速に通報窓口の設置や入院者訪問支援事業の実施の促進をいただきありがとうございます。先般より問題が指摘され続けている孝山会滝山病院については、理事長等交代を行っての再発防止のための抜本的な改革がなされることとともに、身体合併症のある精神障害のある人たちの医療アクセスの向上について障害者団体は注視しています。地域医療構想において精神科も含めたあり方を検討することなど、医療提供体制全体の課題については、東京都のみならず国全体におよぶ大きな課題となっています。再発防止策については、制度疲労についても積極的に取り上げていただき、地方自治法第99条のスキームを活用して国に提言を積極的に行ってください。
■その他事項
- 東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称について)
条例の制定については慎重な審議を行ってください。令和5年度の旅館業法改正の過程で、障害者の合理的配慮の要求が、ややもするとカスタマーハラスメントとの誤解を生じかねない問題が遡上にあがりました。国は、カスタマーハラスメント対策と同時に事業者向けの障害理解の啓発に取り組むこととなりました。東京都カスタマーハラスメント防止条例については、趣旨については賛成しますが、共生社会を阻害するような形とならないために、事業者向けの正しい理解の啓発が必要です。条例の制定にあたり、令和6年障害者差別解消法の改正(民間事業者の合理的配慮の義務化)に鑑みて、必要な啓発資料の作成や実施の援助等について、精神障害を含む多様な当事者団体へのヒアリングや参画をふまえて促進することを担保してください。