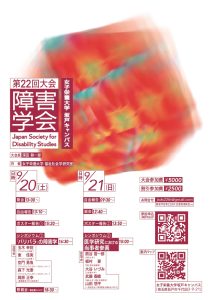【活動報告】第101回お話会レポート(うまく眠るには?、障害の受容についてなど)

真夏の陽気が続く7月27日、東京都障害者福祉会館にて第101回お話会が行われました。初参加の方1名を含む13名の参加がありました。久しぶりにお話会に来た数名の方は、お互いに調子を気づかうなど声を掛け合っていました。
◇うまく眠るには?
「睡眠がとれていない。困るのは日中の不快感で、重たくぼーっとする感覚がつきまとう。それによって意欲も削がれてしまい、新しいことに取り組めない。みなさんは睡眠の工夫など、どうしているのでしょうか」と、一人の方が皆に聞いてみたいと発言しました。
この言葉に応じて他の参加者は次々に、同じような困難について話しました。「私も眠れず困っている。朝日を浴びるなど、できることをさまざま試したが今もうまくいっていない」。「早起き、運動、夜はパソコンやスマートフォンを見ない、ストレッチなど生活に取り入れているが、効果を感じられていない」。
自分の睡眠の傾向についても話題になりました。「入眠は良いのだが、5時間後に必ず起きてしまう」、「私は1時間後にもう目が覚めてしまう」、「中途覚醒がほとんど毎日」。自分の睡眠を客観的に知ろうとしている方もいました。「スマートウォッチを手首に巻いて眠ると睡眠を測れる。スマートフォンのアプリと連動していて結果が見られる。自分に合う対策を考える参考になるかもしれない」と、実際にスマートウォッチを見せてくれました。
睡眠薬のことも皆で話しました。「薬は少し効くが、それ以上に日中に残る感覚があり、頭痛も起こるので、それでは意味が薄いと感じてやめている」。「いろいろな薬を試してきたが、副作用で身体的な反応も出てしまい、漢方薬も効かず、選択肢がなくなってしまった」。
これから睡眠薬を再開しようとしているという方からは、薬についての思いの話もありました。「長期間飲んでいないが、主治医から新しい薬を試してみるかどうかと聞かれたのでよく考えた結果、次の受診時に処方してもらおうと思っているところ。これまでしばらくの間、睡眠薬を飲まずに生活の工夫でどうにかならないかと、意地になってしまっていたところもあるかもしれない。でも今になって、少し飲むのもありかなと考えて、服薬も含めて調整することも一度やってみようと思っている」。

日中の運動が睡眠に良い効果があるというのは、一般的なこととしてもよく目にする情報ですが、お話会では改めてそれぞれの経験を具体的に共有しました。「睡眠に良いと思い筋トレをしていたが、結局自分で加減をしてしまうからなのか、効果がなかった。それで最近、眠れない気晴らしも兼ねて登山をした。必然的に体を動かすことになり良い感覚があったので、また行こうと計画している」。「昨日一日屋外で遊んだが、そうすると久しぶりによく眠れて、今朝は目覚ましにも気づかないほどだった。障害の有無にかかわらず、体を動かすのは大事だと実感した」。「それを聞いて思い出したことがある。これまで自分は、楽しいことで体を動かすとその日は確かに比較的眠れているかも。ただ、苦しいことや嫌なことで動いても眠れないんですよね」。それを聞き深くうなずいている方もいました。
眠りに良いと言われることをいろいろと試すうちに、神経質になってしまったり、それ自体がストレスになってしまったりすることも起こりがちです。一人で自分の睡眠と向き合うと毎日のことでもあり疲れてしまいますが、時々は仲間と一緒に「眠れないね」と話し合うだけでも、随分リラックスできるように思います。
◇障害の受容について
障害の受容という言葉からイメージする範囲は人によって違いがありますが、今回、障害受容について皆に聞いてみたいと言った方からは、その背景が伝えられました。「自分は以前、大きく自分の障害を受け入れたと感じたことがあり、それから生きやすくなった。でも、自分が分かっていない部分もまだまだある気がしていて、それらへの向き合い方もつかめたらより良い生活ができるのではないか。他の方も、日々の細かい受容というか、自分を受け入れられるようなことがあったりするのか、聞いてみたいと思った」。
この話について、「自分もぜひ聞きたい」という方がいました。「自分はたぶん障害受容ができていない。うまく受け入れているようにみえる人の、うまい部分を取り入れられたらいいのになと思う。受容しているようにみえる人は、折り合って生活していて、きっと自分のことが嫌いじゃないのだろうなと思う」。
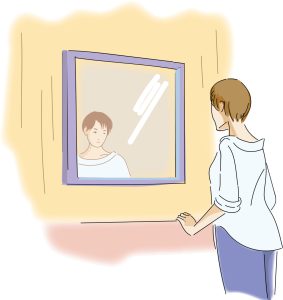
障害についてのネガティブな情報も飛び交う中で、障害のある自分を受け入れようとするのは大変なことになる場合も多く、諦めたくなってしまうこともあります。そのような中でも、例えば自分の肌感覚がより合う環境に身を置いたり、人と比較するのではなく自分自身のゆるりとした目標をもつことで、徐々に障害のことを受け入れる感覚をもつことにもつながるのではないか、という話になりました。
一方で一人の方から、「今の環境でやっていきたい気持ちもある。例えるなら、自分は本来は塩水で生きる魚ではないのにそこにいたら息をするのも一苦労だ。それでも真水に行かずにどうにか塩水の中でやってきたので、ここでどうにかもがくことをあきらめたくないと思う」という思いの共有がありました。
これを受けて、「必ずしも0もしくは100ではなくても良いかもしれない」という考えが挙がりました。「少しだけ真水を加えてみる。ほんの少し環境が変わるだけで、自分の障害との向き合い方も変わるかもしれない。見方を変えれば、自分にとって居心地のよい環境に整えることは、障害のない人にとっても、実は過ごしやすい環境になることがある。そして、今ある環境そのものを少しずつ変えていくことができれば、他の人も、自分自身も、“実はしんどかった”と声をあげやすくなるのかもしれない」。

障害を受容すべしというメッセージが、どこか当事者に一方的に向けられることは少なくありません。しかし本来は、自分自身のペースで、自分を受け入れていく感覚こそ大切にしていきたいものです。そもそも障害の受容とは、当事者だけが担うものでも、一人でできるものでもありません。むしろ、当事者の仲間を含めた周囲とともに考え、関係のなかで育んでいくプロセスなのだと思いました。
◇おわりに
一人ではない、仲間がいると感じられる時間や場は、今の時代性もあり実は多くの人にとって得難いものなのかもしれません。お話会もそのような場のひとつであるよう、これからもみなさんと一緒に開催していきます。この取り組みは、公益推進協会釋海心基金の助成により実施をしています。(相良)