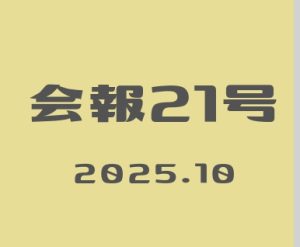【活動報告】9.17障害年金不支給増問題ー厚労省との懇談報告
2025年9月17日、厚生労働省において障害年金の不支給増加問題をめぐる意見交換を行いました。当日は厚労省事業管理課・年金課らの担当者に対して、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)、全国「精神病」者集団、特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構(コンボ)の関係者とともに懇談に臨みました。
厚労省からは、2024年度の新規申請において精神障害のある人らの不支給件数が増加傾向にあるとの報道を受けて実施された 「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」(2025年6月11日公表) を基に再審査を進めており、その結果に基づいて2025年度内に不支給判定の点検を終え、速やかに個別通知を行う予定であることが説明されました。また、認定医の選定方法の見直しや審査会に福祉職を加えるなどの改善策も進められることについて説明がありました。
他方で、当会としては、この不支給増問題が単なる運用上の課題にとどまらず、制度への信頼そのものを揺るがす重大な事態であると受け止めています。報告書はあくまで基準に沿った運用であったと結論づけていますが、実際には職員による等級案の作成や認定医への影響力などを通じて、静かな厳格化が進み、不支給増加につながった可能性は否めません。さらに、「週4日働けているから軽度」といったような旨の就労を重視したような表現ぶりが散見されることから、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(2016年9月策定) において「就労の有無のみで支給・不支給を判断してはならない」と明記されている趣旨に反しています。こうした判断が続けば、「少しでも社会参加すれば不支給」という逆転現象を生み、障害年金制度の趣旨である「生活基盤の保障と社会参加の支援」を損なうことになることを深刻に憂慮しています。
また、認定理由が簡略にとどまり、本人の語りや生活実態が十分に反映されない審査構造も大きな課題です。当事者にとって納得できる説明が得られなければ、制度に対する不信と諦めを生むことは避けられません。
そのため当会は、「働ける=支援不要」という判断を改め、支援を受けながら働くことを正当に評価できる制度へ転換することを含めて、実態に合わせた制度設計のあり方を見直すことを提言しました。とりわけ、2019年の障害者雇用促進法改正に伴い、精神障害者の雇用義務化が実現したことで、多くの当事者が配慮のある職場や福祉的就労の場を通じて社会参加を果たすようになっています。
この変化は、働くことが必ずしも「障害が軽い」ことを意味するのではなく、支援環境や合理的配慮があって初めて可能になっている現実を示しています。にもかかわらず、現行の年金認定では就労そのものをもって支給停止や不支給の根拠とする判断がなお残っています。こうした制度運用は、雇用政策の進展と矛盾し、結果として当事者の社会参加を阻害する危険があります。
したがって、障害年金制度の設計も、就労を排除要因とするのではなく、むしろ支援と就労を両立させる形で生活基盤を保障する方向へと見直す必要があります。当会は、この視点こそが2019年以降の社会状況を踏まえた制度改善に不可欠であり、今後の改革の出発点であると考えます。
今回の不支給増問題は、日本が批准している 国連障害者権利条約の観点からも深刻に受け止められるべき事案です。2022年に公表された総括所見では、パラグラフ59–60(第28条) において障害年金を含む所得保障の低水準が懸念され、障害年金額の見直しを当事者団体と協議して行うよう勧告しています。さらに、パラグラフ55–56(第26条) では日本の制度が依然として医学モデルに依拠していることが懸念され、人権モデルへの転換が求められています。これらは、条約第4条3項が定める「障害者当事者団体の参画」とも密接に結びついています。
こうした国際的勧告に照らしても、本人の声を反映し、社会参加を支える制度への改革は不可欠です。今後も当会は、関係団体と協力しながら、障害者権利条約に基づき、当事者の声を制度改革に反映する取り組みを行っていきます。
■参考資料
・厚生労働省(2025年6月11日公表)
「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」
・厚生労働省(2016年9月策定)
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
・国連障害者権利委員会(2022年9月)
「日本に関する総括所見(CRPD/C/JPN/CO/1)」(外務省和訳版)
・一般社団法人精神障害当事者会ポルケ
障害年金「不支給増」問題への見解