【活動報告】第104回お話会レポート(近所での偏見の目があること、相談相手の見つけ方など)
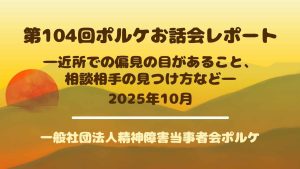
10月9日、今回のお話会は平日夜の開催となりました。会場の東京都障害者福祉会館の窓の外も、開始の18時にはすっかり暗くなり、季節の移り変わりの速さを感じました。
今回は、急な気温変化や台風接近による体調への影響もあったのか、当日キャンセルの連絡が数名からあり、初参加の方4名を含む9名の参加でした。
◇近所での偏見の目があること
ある参加者から、「現在近所でのトラブルがあり困っているので、みんなの経験や意見を聞いてみたい」との投げかけがあり、今回はまずこのことを皆で話し合いました。
「今の自宅に住み始めてからずっと、近所の人たちとの関係も良かった。ところが、ある時から挨拶もしてくれなくなり、なぜだろうと思っていた。どうやらいつの間にか自分が障害者だとわかったらしく、はっきり『○○病だから何を言っても分からないよ』『あの人は障害者だから』という声が聞こえてきたことも。
ショックだったが、『自分の空耳かもしれない』『症状によるものかもしれない』と思い、色々考えて相談したり、薬も増やしてもらったりもした。しかしやはり本当に言われているようだ。相談機関からは録音も勧められたが物理的に難しく、どうすればよいのか悩んでいる」。
このことについて、皆が共感を示し、また他の参加者からも経験が共有されました。
「『そんなふうに』思われているなと感じることはある。ヘルプマークも付けているし、視線の動きなどが他の人と違うように見えることもあるのだろう。近所で度々、若い人たちからちらちらと見られて笑われることがあり、腹は立つけれども、『向こうからすれば知らない世界なのだろうから仕方ない』とあきらめている」。
見た目ではわからない障害とされる精神障害。周りにわからないために理解を求める難しさを私たちは日々感じています。それに加え、「わかった」際にこのように偏見の目を向けられることもあり、八方塞がりのつらさがあります。

また、実際に周囲から障害に関して悪口や差別的なことを言われていても、相談の場ではまず「幻聴や思い込みではないか」と言われることが少なくありません。そうすると、苦しさの原因が自分にあるのではないかと、自分を疑わざるを得ないしんどさを感じます。
「近所の人たちとまた仲良くしたいとまでは思いません。ただ、他の家にも聞こえるように差別的なことを言うのはやめてほしいのです」。偏見の根深さを改めて感じる、私たちにとってとても大事なテーマについて、これからも皆で話し合っていきたいと思いました。
◇相談相手の見つけ方
「精神障害のことも、日常の悩みについても、この人に相談して良いのだろうかと遠慮してしまい、話せないことがある。相談相手をみんなはどう見つけているのか、どんな人が自分に合うと感じているのかを聞きたい」という問いかけがありました。するとまず、「自分も病気のことや日常の困りごとを相談したいのだが、日頃の生活の場で、中々その相手を見つけられないでいるので、自分も聞いてみたい」との声が上がりました。
これらに応じて、専門機関の支援者に相談しているという経験が数人から共有されました。「地域のカウンセラーに、生活のことや家族のことなどを聞いてもらっている。気さくな人で話しやすい。区の無料事業というのも助かっている」「通院先の精神保健福祉士に定期的に相談する。心身の症状については担当の医師につないでくれたりもする」。他にも訪問看護や診察の際に相談するという人もいました。
それから、専門職に限らず、相談するときの意識や相談の仕方についても話題になりました。「将来的に、困った時には一緒に考えてくれるような人ができたらいいなと思うがどうしたらよいのだろう」、「大事な相手ほど迷惑をかけたくないと思って相談できない」、「踏み込み過ぎたときにはごめんねと言える関係なら、思い切って相談するのも良いのでは」。

これを聞いてテーマをあげた人は、「相手との距離ということで考えた時、自分は距離をとることはできるけれど、いい具合に距離を詰めることができなくて、だから相談相手も見つからないのかなと感じた。反対に、相手の話だったら聞くし、必要なら手助けもしたいと思うのに、自分のこととなると誰かの手を借りることが難しくなってしまうんです」。
仲間同士相談し合える人を見かけるとうらやましい、というつぶやきもありました。人との距離感は常に私たちのテーマでもあります。これも、「人との距離感をつかむのが苦手」という障害特性とされることがあり、そういった言葉に私たちは自分をより責めてしまいます。また、特にとてもつらい状態にあるときには相手の負担まで考えることが難しく、無意識に相談し過ぎて相手が疲れてしまうなど、「自分が失敗した、迷惑をかけてしまった」と感じている人も多くいます。
ですが、やはりつらいときにはお互いに頼ったり頼られたりしながら進んでいきたいものです。その感覚をつかむのは難しいことではありますが、お話会での共有から、改めて人間関係のあり方についてもふと振り返ることができました。

◇おわりに
お話会の最後、感想の時間には、
「自分の話について、新しい視点でみんなから話してもらえてよかったです」
「自分の悩みは他の人の悩みでもあり、他の人の悩みを聞いて自分のことでもあると感じました。それを知るだけでも楽になりました」
などの言葉が共有されました。仲間がここにいたのだと感じられる場があるだけで、ふっと力を抜くことができます。これからもみなさんのお話会へのご参加をお待ちしています。
この取り組みは、公益推進協会釋海心基金の助成により実施しています。(相良)

_page-0003-300x212.jpg)
