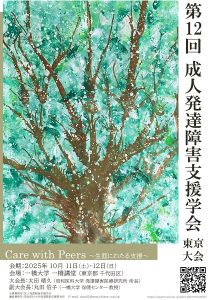【活動報告】東京工科大学ゲスト講師を務めました
精神障害当事者会ポルケは、以前より協力している東京工科大学医療保健学部リハビリテーション学科の作業療法士養成課程において、7月11日、当会のメンバー5名がゲスト講師を務めました。対象は3年生の皆さんで、授業では精神科作業療法における面接のインテーク場面を模擬的に体験していただきました。学生の皆さんはしっかりと準備を行い、関心をもって私たちに向き合ってくださいました。
また同月には、精神看護学のクラスにもゲスト講師として参加し、当事者の視点から日常生活や支援に関する体験を語る機会をいただきました。
今後も、私たち当事者の生活を支える専門職の養成に関わる授業に、積極的に協力していきたいと考えています。
■ゲスト講師の一人を務めた加藤さんの感想
東京工科大学で作業療法士の勉強をなさっている学生さんと模擬面談をしました。対象学年が3年生。8名の学生さんが2組ずつ面談します。面談は、学生さんが質問して当事者が答えるという形です。
先ずは自己紹介。去年の授業で顔見知りになった方もいらして、緊張中にも穏やかに始まりました。さて、初めは男性2人。緊張した面持ちでした。私も緊張していいます。続いて次々と面談しますが、緊張感は徐々に取れていったようです。笑いもありました。
私は、強迫性障害、双極性障害、アルコール依存症の診断を受けています。面談は主に、アルコール依存症を見据えた内容になりました。朝から飲むんですと言いました。
学生さんが「今朝は飲みましたか?」と言ました。面談の時間は、午前11時です。少しドキッとしましたが「飲んでいません」と。このような直接的な質問は、良いと思いましたが、しかし、これは諸刃の剣かもしれないとも思ったのです。胸をえぐるような質問は、医師が時よりします。それによって、支援者と当事者の間に上下関係が生まれてしまうのではとも思いました。ただこの質問はそのような関係性をうむ危険があるものの、端的に聞いてみるのは大事な事とも思います。上下関係、つまり、支援者に「見透かせている」状況に埋もれる優位、不利はなかなか払拭出来ないのでは?とも感じました。でも、良い質問です。続いて、飲酒の量です。焼酎の水割りで6杯位と答えましたが、それに関しては、続く質問はありませんでした。体調の管理などを聞いて欲しいと思いましたが、それほど深堀する内容ではなかったかもしれません。
依存症とは無関係ですが、大事なのは生活全般に関わる事です。炊事、洗濯など日常生活の事です。私は一人暮らしですが、日常生活で困ったことはありません。日常生活に含まれますが、社会生活。最小限の対人関係は行っています。この辺りは深堀り出来なないでしょう。全般に渡って、生活に関して困りごとはありません。
強迫性障害に関わって当事者会の話題が出ました。私は以前、強迫性障害で苦しんでおり、藁にもすがる思いで当事者会に参加しました。「当事者会はどんな様子でしたか?」という質問に、寛解に向かうヒントを沢山貰いました。当事者会については一通り話しましたが、学生さん達がどこまでピンときたか分かりません。体験してみなければ、なかなかそのニュアンスは伝えられないと感じました。それは仕方ありません。「当事者会でどこが心に刺さったか」という質問がありましたが、これは深いところを刺していると思います。
さて、全般的な感想ですが、当事者に対して「その人生を肯定する」という取り組みがあり、素晴らしいと感じました。これはなかなか出来ません。ポジションによる優劣は、いつどのような場面でも軋轢が生まれます。自己決定が出来るスタンスでの面談は素晴らしかったです。これか学生さんたちが生み出す当事者との関係を期待しようと思います。素晴らしい時間をありがとうございました。満足感のある時間でした。